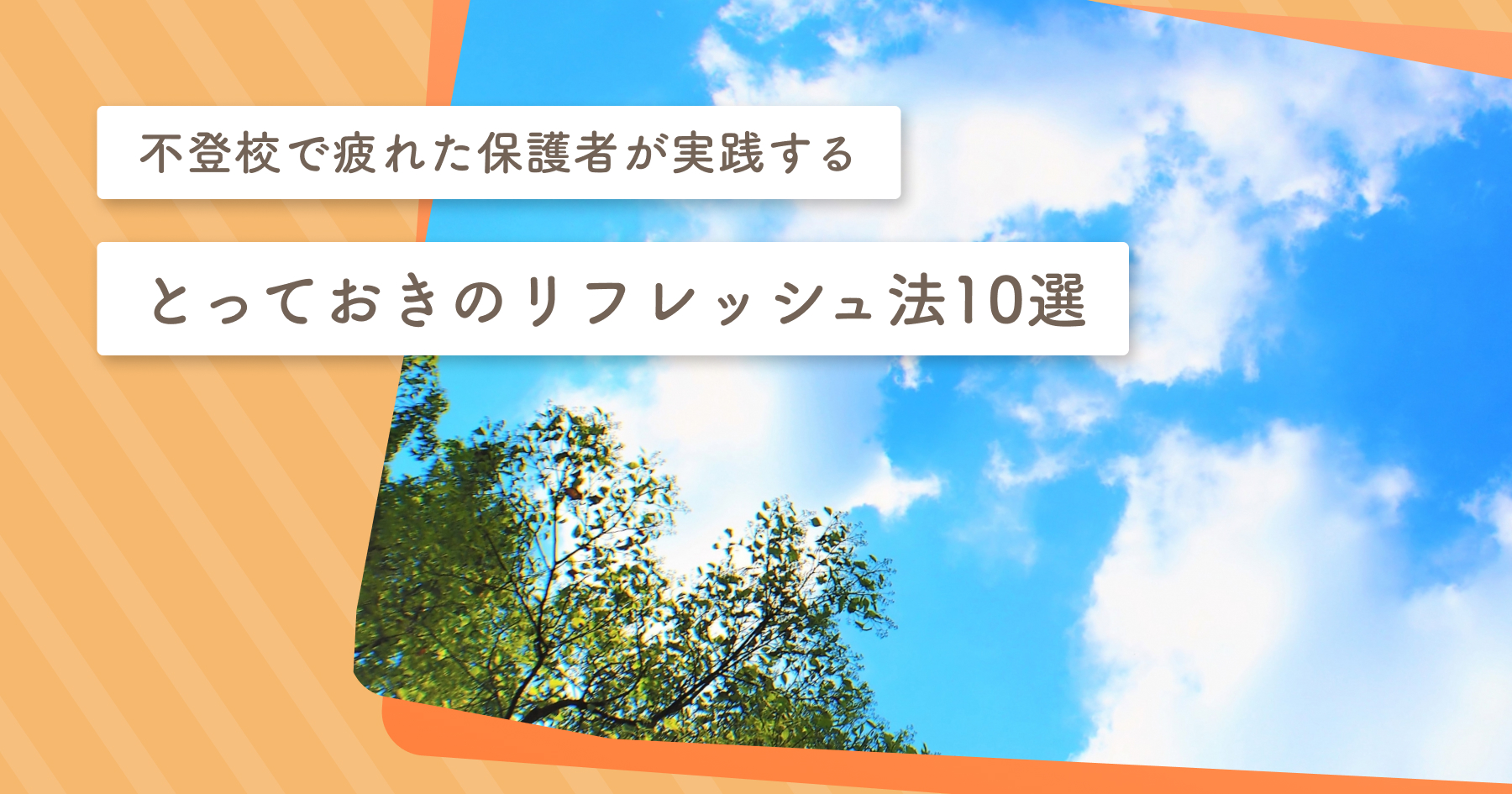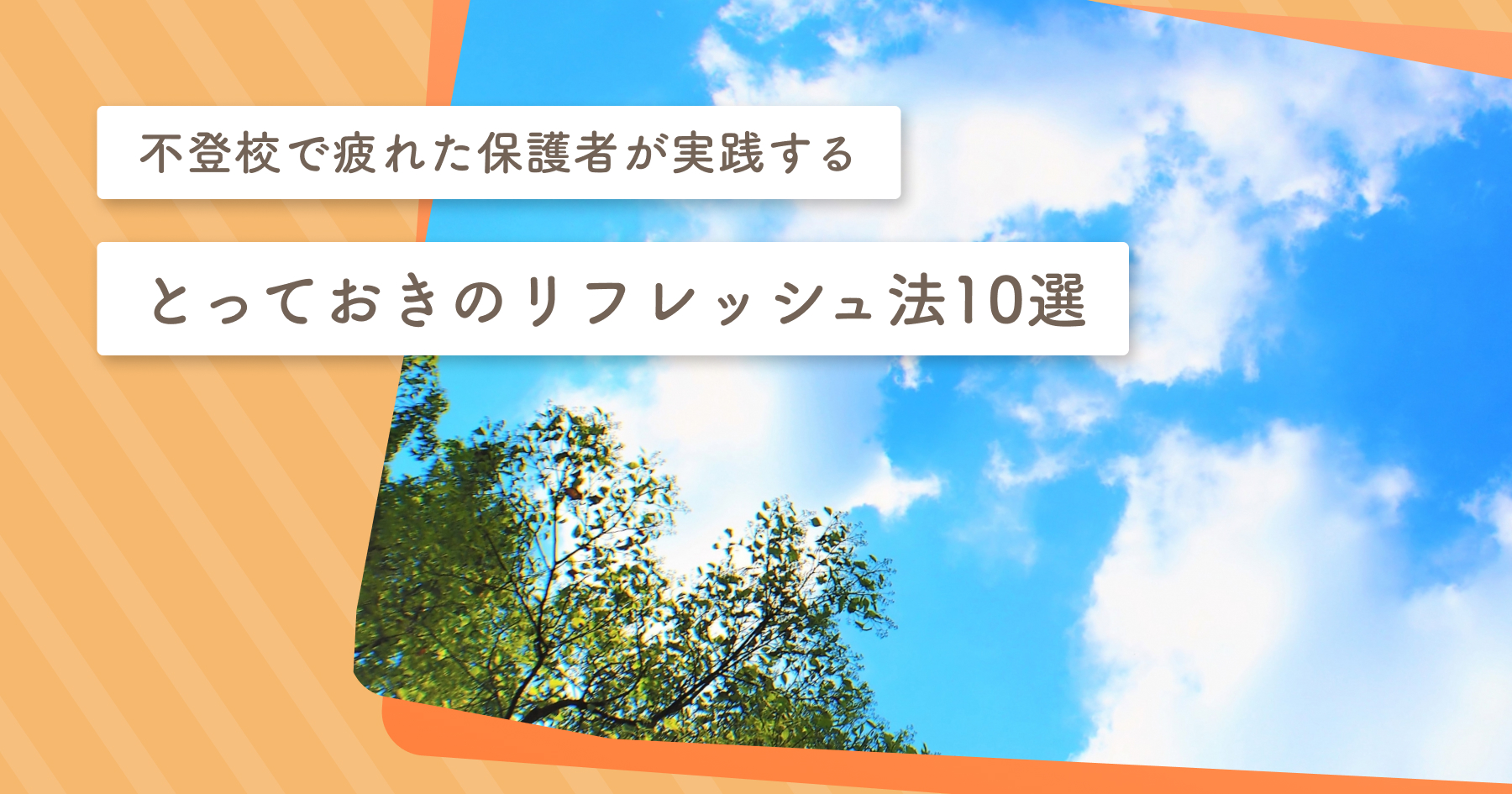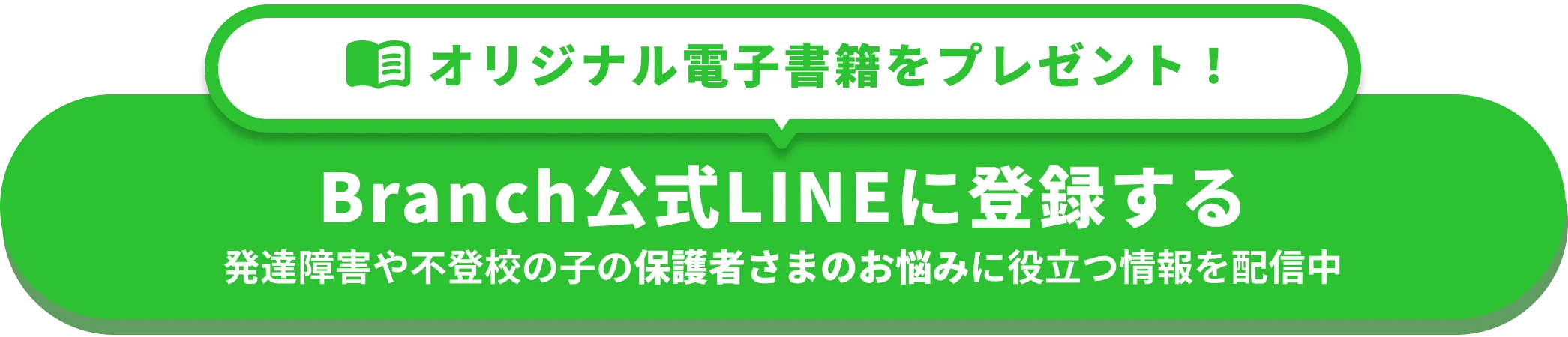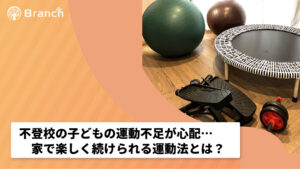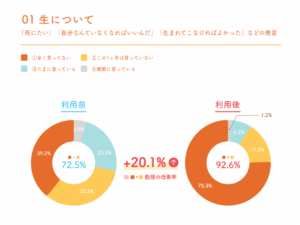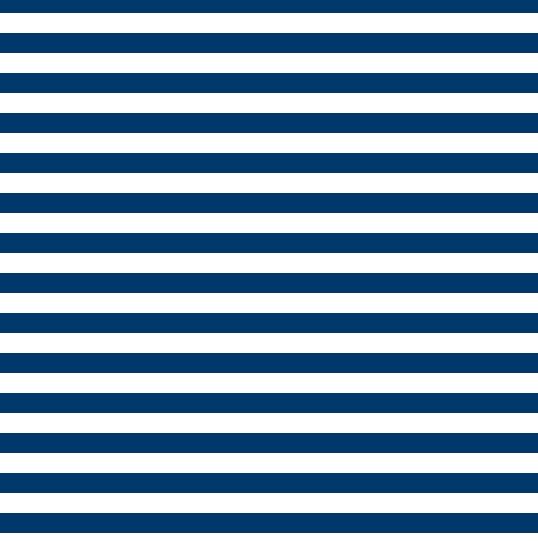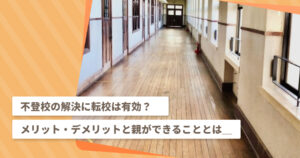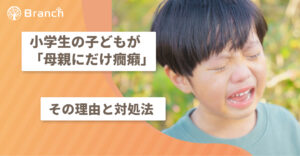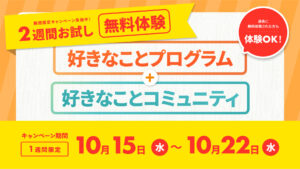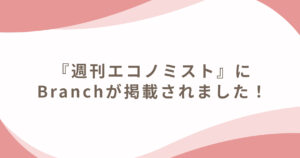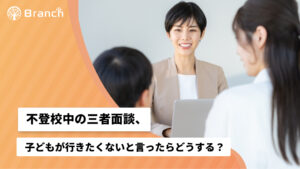こんにちは。不登校や発達障害の子どもと保護者さんのための居場所、Branchコミュニティです。
子どもが不登校になると、親自身も「しんどい」「疲れた」、そんな気持ちになることが増えるのではないでしょうか。
「親が笑顔でいることが、子どもにとっては一番」と言われ、その言葉すらプレッシャーになったことのある方も少なからずいると思います。
今回はそんな保護者の方に向けて、しんどい気持ちを少しラクにする考え方や具体的な相談先について紹介していきます。
不登校の子どもを持つBranch保護者の方の体験談や、不登校を経験したお子さん自身のストーリーも紹介しますので、是非読んでみてください。
メンターや友だちと、安心して「好き」を楽しめる、学校外の居場所。
Branchは、信頼できる大人のメンターと、学校外の友だちと、安心してつながれるオンラインの居場所です。
不登校や発達障害の子どもたちが「好きなこと」を通じて自信がつき、社会とつながることを目指しています。
\メンター2回&コミュニティ2週間&詳細なレポートが無料 /
子どもが不登校になるとなぜ親は「しんどい」と感じるのか
子どもが不登校になると、親も同時にしんどさや辛さを感じることは珍しくありません。
この記事を読んでいて、まさに今その真っただ中!という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
親が「しんどい」と感じる理由は様々ですが、主に以下のようなものがあります。
子どもの将来への不安
学校に行かなくなることで勉強の遅れや社会生活の経験の減少が生じることから、子どもの進学や就職といった将来に対して親は強い不安を感じます。
その不安感が精神的な疲労感、しんどさに繋がっていきます。
周囲からのプレッシャーと責任
子どもの不登校の原因が親の「甘やかし」「育て方の問題」と周囲から言われたり見られたりすることで、自分を責める気持ちが芽生えてしまい、辛くなってしまいます。
 保護者
保護者周りの目が気になります。住んでいる所が地方なので、干渉する人が多く、日中自由に歩き回る事ができない
社会からの孤立感
不登校初期の子どもは特に保護者との分離不安を感じることも多く、親がそばを離れることを極端に嫌がる場合があります。
そのため、親自身の行動が制限され、外出がしにくくなったり、仕事に行くことも難しくなることがあります。
それにより、親は社会からの孤立感を強く感じてしまいます。



母子分離不安で、24時間母親から離れられなかった時期はきつかったです。仕事との兼ね合いに苦労したことと、自分の時間が全くなくてきつかったです
数年間自分の友達と会うみたいな時間が全く取れなくて疎遠になってしまった友達もいるのも悲しいです
学校とのやり取りの負担
毎日の欠席連絡やプリントの受け渡しといった事務的な事柄の煩雑さ、それに加えて学校から登校刺激がある場合は、親の心理的負担に一層拍車をかけます。
また、子どもが不登校でもPTAの役はこなさなければならないことも多く、辛いといった声も多く聞かれます。
他にもBranchの保護者の方からはこのようなコメントもあり、色々な側面からのしんどさが伝わってきます



子供の昼食の準備が負担



登校してる他の子をみると比較して悲しくなる



午後だけ学校へ行くとかたまにあるので、なかなか登校をしてくれる期待を捨てきれずに、行く行かないで気持ちが振り回されてしんどい時があります
- 子どもの将来への不安
- 周囲からのプレッシャーと責任
- 社会からの孤立感
- 学校とのやりとりやPTAの負担 など
不登校のしんどい気持ちから抜け出すための考え方
しんどい気持ちが続くほど、心身や生活面にも影響が出てきます。
では、どうすればしんどい気持ちから抜け出せるようになるのでしょうか?
完璧な親を目指さない
「親だから~すべき」といった社会的な規範を一度捨てて、完璧な親・理想の親を手放してみましょう。
親も一人の人間。落ち込む日があっても、感情的になる日があっても当然です。
「ちゃんとできない日があってもいい」と自分に許可を出すことが、心の余裕を取り戻す第一歩になります。
自分の考え方のクセや偏り、思い込みを改善するのに「認知行動療法」が役立ちます。
認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy)はCBTとも呼ばれ、ストレスなどで固まって狭くなってしまった考えや行動を、ご自身の力で柔らかくときほぐし、自由に考えたり行動したりするのをお手伝いする心理療法です。
そもそも認知行動療法(CBT)ってなに? | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター より
カウンセリングでも用いられる心理療法ですが、アプリやワークブックで気軽に取り組むこともでき、知っているだけでも自分の考え方のクセに気付くことができるのでおすすめです。
減点方式ではなく加点方式で考える
100点満点から、できなかったことを減点していくのではなく、0点からできたことを加点していく「加点方式」の考え方をしてみましょう。
できなかったことより、できたことに目を向けると、自分の頑張りに気づけて前向きな気持ちになれます。
そして、親である自分の「できた」を認めることができると、子どもの「できた」にも自然と気が付くようになります。
そんな時は、自分も子どもも思い切りほめてみてくださいね。
子どもにやってほしい行動が100%完了してからほめるのではなく、行動に取り掛かった時点・25%の段階でほめる、これが25%ルールの考え方です。
【例】お風呂掃除をお願いしたら、完了した時点でほめるのではなく、「分かった」と返事をした時点や立ち上がった時点でほめる
25%ルールでほめると、子ども自身のほめられる回数は必然的に増えていきます。ほめられると嬉しいものですよね。
特に不登校なりたての子どもの中には、不登校である自分に対して罪悪感を感じている場合もあるので、たくさんほめて自信を取り戻してあげましょう。
「長い目」で考える
不登校の状態は、ずっと続くわけではありません。
表に見えなくても子どもの内面は少しずつ成長しています。だからこそ、焦らず、長い目で見てあげてください。
今の状態を「停滞」ではなく「充電」ととらえ直して、子どもとの貴重な時間と考えると、自然と子どもの変化にも目が向くようになります。
不登校のしんどい気持ちから抜け出すための具体的な方法
しんどい気持ちをゼロにするのは難しいですが、色々な人に相談したり頼ったり、情報を入手しておくことで、具体的な手立てが見えてきて、今よりも楽になります。
自分自身のケアをする
親が自分自身をケアすることも大切です。
育児のさなかはどうしても子ども優先になることは避けられません。とはいえ、その状態が休みなく続くと、自分自身が失われたような気持ちになったことのある方は多いのではないでしょうか。
子どもや家族のケアを優先していると、自分のケアをすることは忘れてしまいがちです。
Branchでも、親が自分自身を大切にする、自分のケアをすることの大切さはよく話題になります。
「お気に入りの音楽を聴く」「あたたかいお茶を淹れてひと息つく」といった、ささやかなことで大丈夫です。
自分のための時間を少し作って、自分を労わってみてください。



仕事していた時以来のネイルに行ったらかなり気分が上がりました
目に見える自分ご褒美や少しだけでも1人時間は必要と痛感
相談先とつながる
子どもが不登校になると、親自身の行動範囲も狭くなり孤立感を深める場合が多いです。
そんな時、信頼できる相談先があると、すぐに悩みが解決しなかったとしても、孤立感がやわらぎ気持ちのしんどさの解消には大きく役立ちます。
市区町村の相談窓口やカウンセラーなどの専門家に話を聞いてもらうことはもちろん、同じ悩みを持つ親同士の繋がりを持つと「自分だけじゃない」「仲間がいる」ということが分かり、気持ちが落ち着きます。
先輩保護者の体験談を聞いて見通しを持つことができるのも心強いですね。
子どもについての相談だけでなく、親自身のケアのために相談先を活用しましょう。
相談先1 学校関係者
養護教諭、スクールカウンセラー、特別支援コーディネーターなど、話しやすい学校関係者に相談するのは身近で手軽な手段です。
たくさんの親子を見ているので、色々な経験談を聞けるメリットがあります。
ただ、なかなかこちらの状況を理解してくれない相手だったり、良かれと思って登校を促してきたりされるとかえってしんどさが増してしまうので、その場合は無理をせず別の相談先を頼ると良いでしょう。
相談先2 国や地方自治体の相談先
市区町村のこも家庭支援課や、児童相談所でも相談に乗ってもらえます。
方法も、電話や対面以外にLINE相談もあるので、外出やまとまった時間を作るのが難しい場合でも気軽に相談することができます。
相談先3 カウンセリング
プロのカウンセラーに話を聞いてもらうのおすすめです。
カウンセリングには対面やオンラインなど様々な形態があり、費用にも差があります。
主に、医療機関や民間のカウンセリングオフィスなどで行われることが一般的ですが、それとは別に無料や比較的安価に利用できるものもあります。
- 医療機関でのカウンセリング
- カウンセリングオフィス
- 加入している健康保険や、民間の医療保険の加入者向けサービスとしてのカウンセリング(付帯サービスとして無料で使える場合があります)
- 大学の心理学部が行っているカウンセリング
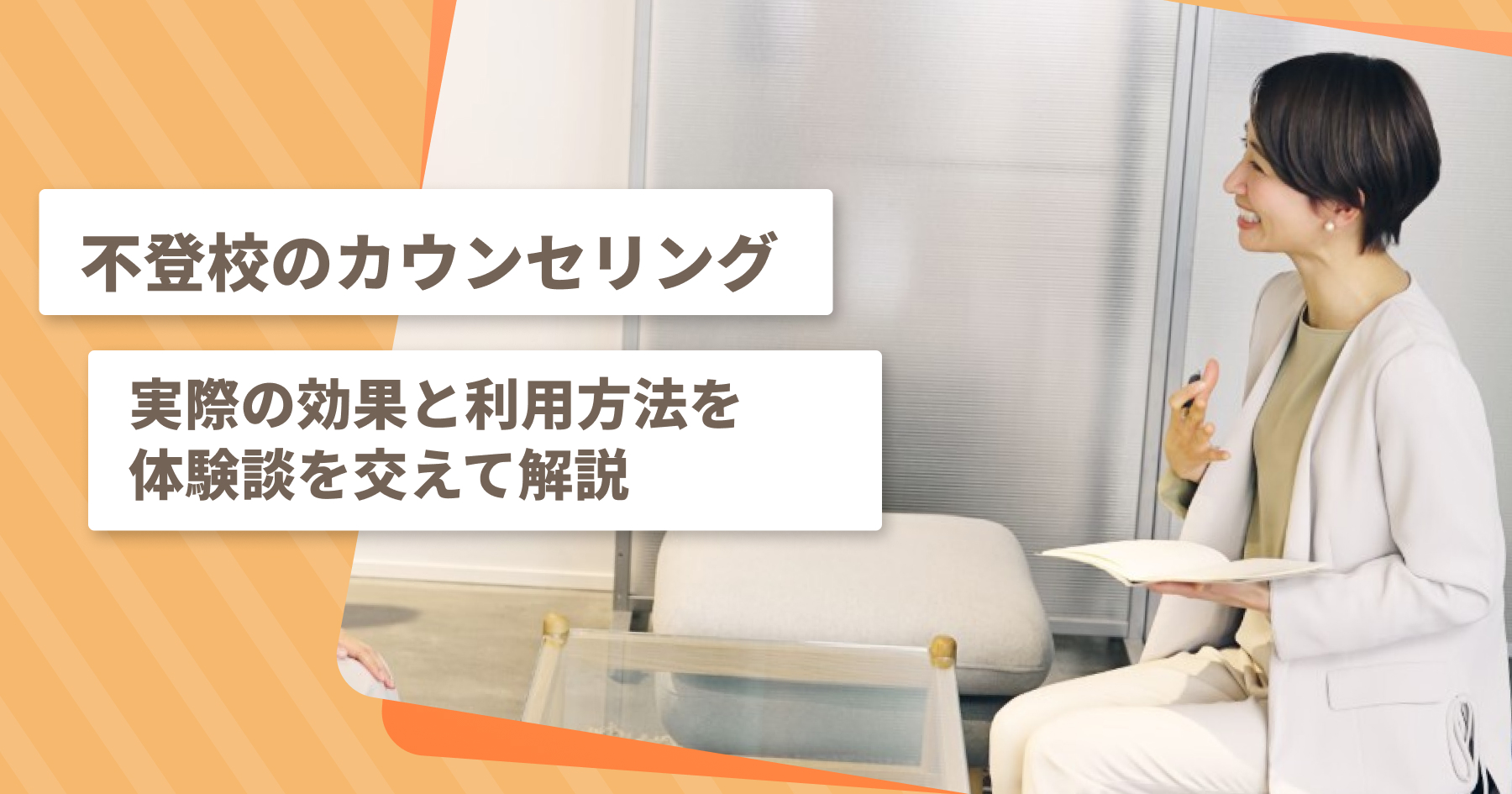
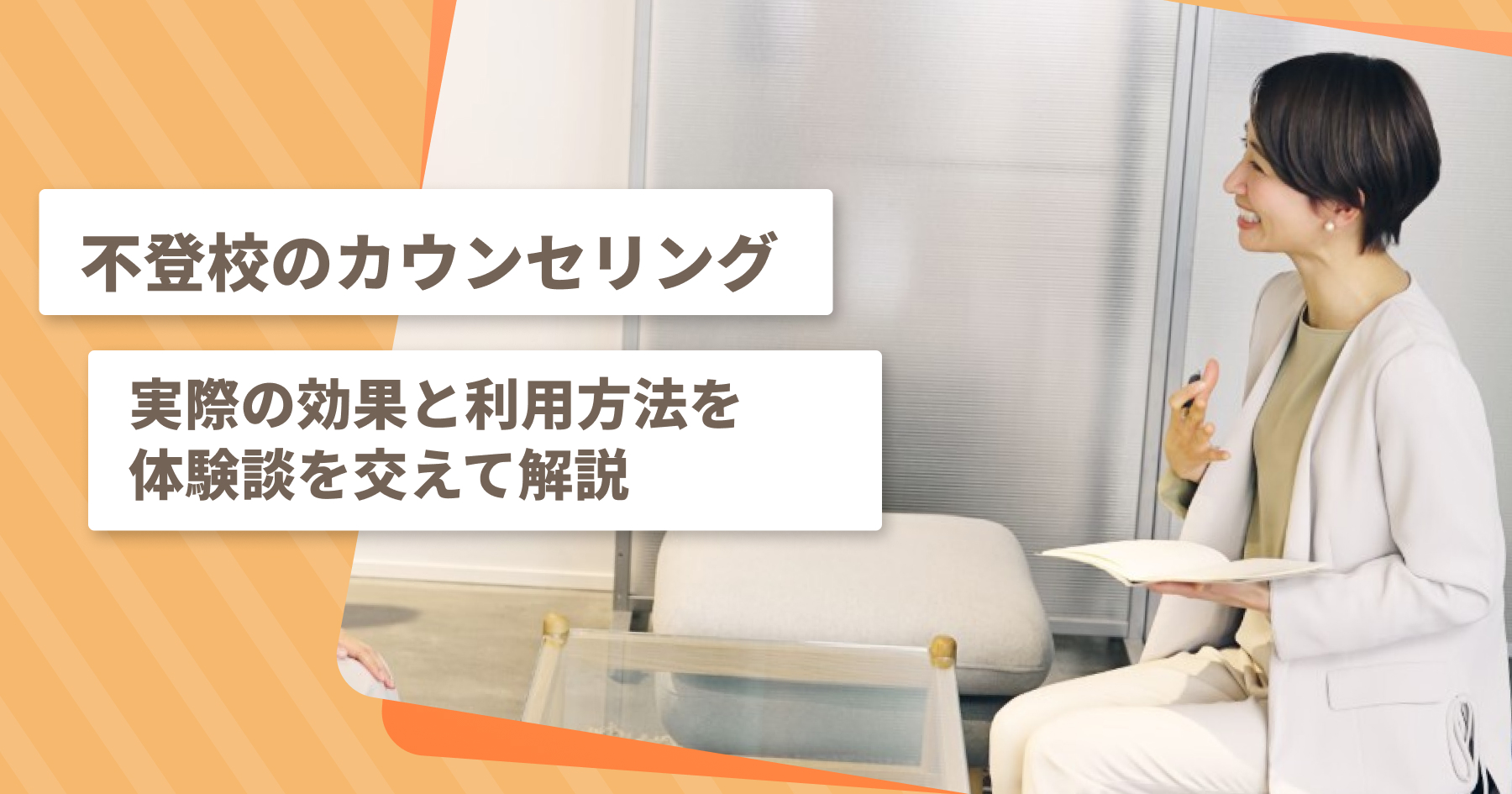
相談先4 親の会やSNSなど
不登校の悩みはなかなか友だちや同僚など、身近な人には相談しづらいものでもあります。
そんな時、頼りになるのは、同じ悩みを持つ仲間=ピアのちからです。
不登校の親の会や、SNSのグループチャット、もちろんBranchオンラインコミュニティなど、同じ悩みを分かち合えると気持ちが楽になったり、居場所や進路に関する情報も入ってきやすくなります。
- LINE相談
- カタリバ相談チャットhttps://www.katariba.or.jp/support/
- お母さんのほけんしつ(お母さんお父さんの相談窓口)https://www.npo-keydesign.org/hoken-shitsu-for-parents/
- 不登校の親子の居場所
- トーキョーコーヒー 「登校拒否(トウコウキョヒ)」のアナグラム。全国にある親のための居場所です
- トーキョーコーヒー 「登校拒否(トウコウキョヒ)」のアナグラム。全国にある親のための居場所です
- 地域の親の会やSNSのグループチャットへの参加


相談先5 SNSや外部リソースの活用
他にも、Branchオンラインコミュニティでは
- SNSで不登校のエピソードをつぶやく
- 日記に気持ちを書き出す
- 見守りカメラを利用して子どもと離れる時間を作る
- 昼食は冷凍食品やおにぎりを用意して子ども自身に用意させる
- 夕飯を作る元気がないときは宅配を利用する
などなど、様々な方法で、しんどさを減らしているといった声が聞かれました。
不登校を受け入れるという選択肢について考える
今の社会において、不登校という選択は、必ずしも悲観することではありません。
しかしながら、具体的にどんなフォローをすればいいのか、またどんな進路に進んだお子さんがいるのか、見通しが立たないと不安も大きく、しんどさの解消になりません。
ここでは不登校を受け入れた先にある生活や進路について、その選択を支えるツールやモデルケースを紹介します。
不登校でも学習できる
不登校でも教科学習はできます。
学習面のサポートには様々な手段があります。
利用料金は無料のものから有償のものまで様々で、民間のものだけでなく、自治体が不登校支援の一環として提供している場合もあります。
- 自治体の不登校支援を利用する
- 適応指導教室で学習する
- 自治体の不登校支援を利用する
- 無料のオンライン教材
- みんな何つかってる?ホームスクールの教材リスト | HoSA
NPO法人 日本ホームスクール支援協会が紹介しているホームスクール用の教材リストです
- みんな何つかってる?ホームスクールの教材リスト | HoSA
- 有料のオンライン教材
- 無学年方式のものから学年ごとのものまで幅広くあります
- 学年ごとの教材でも、お子さんの在籍学年ではなく、学習進度に合った学年を選ぶことが可能な場合もあります
- 民間の塾・家庭教師
- 不登校のお子さん向けの塾や家庭教師もあります
- 個別指導が多いため割高ですが、オーダーメイドの学習をサポートしてもらえます
- フリースクール
- リアルの教室だけでなく、近年はオンラインフリースクールも増えてきました
- 同じ不登校という共通点を持った仲間との出会いもあります
好きなことの探究による学び
教科学習とは別に、子どもの好きなことを探究することも立派な学びです。
自分の好きなことなので自分から取り組む、つまり主体的に活動することで、責任感や判断力、問題解決力などの非認知能力を伸ばすことにもつながります。
何よりも好きなことを通して、上達や達成感を感じられ自信をつけることができます。
学校に行かないからこそできる学びの形です。
不登校でも進学できる—多様な進路の選択肢
不登校は、必ずしも進学を妨げる要因にはなりません。
ここ数年で、進路の選択肢は多様になりました。
例えば公立の学びの多様化学校やチャレンジ校、そして民間の通信制高校など、子どもの状態や興味に合わせて柔軟な進路選択ができるようになってきました。
設置が進む「学びの多様化学校(旧・不登校特例校)」
文部科学省は、2023年から5年後までにすべての都道府県や政令指定都市に学びの多様化学校を設置し、将来的に全国で300校設置することを目指すとしています。
これにより、既存の学校での学びが難しかった子どもたちにとって選択肢が一つ増えました。
不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校のことです。
令和7年度現在、全国で58校(公立37校、私立21校)が既に設置されています。
学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧 :文部科学省
多様な進路の選択肢
義務教育終了後の進路は多様です。
お子さんの興味関心、学習進度、生活リズムなどを加味しながら、義務教育時代よりも柔軟な選択ができるようになるとも言えます。
以下は義務教育終了後の進路一例です。
- 公立のチャレンジ校・エンカレッジスクールなど
- 不登校などにより、十分な学びが叶わなかった子どもに向けた高等学校です
- 通信制高校
- 学校にもよりますが、民間の通信制高校は登校する日数を選ぶことができます
- 高等専修学校
- 専門的な職業に就くための実践的な教育を行い、専門知識と技術を身に付ける学校です
■義務教育期間の子どもを対象とした、メタバースを利用したオンラインスクールや通信制の学校もあります
■近年は、内申書の欠席日数欄を削除する都道府県も増えてきました
不登校の先にある未来に向けて
不登校期間は人生のほんの一部です。
その先の未来に繋がる「進路」と「自立」に関するBranchのPodcastを紹介します。
進路:中学から高校への進学をしたBranchの高校生メンターさんへのインタビュー
進路:高校・大学への進学したメンターさんへのインタビュー
進路と自立:キズキ共育塾さんとの対談
終わりに
子どもが不登校になると、親として不安やしんどさを感じるのは、ごく自然なことです。
それは決して親の責任や努力不足によるものではありません。
不登校は子どもの将来を閉ざすものではありません。
学校以外にも学びや成長の場はあり、子どもはそれぞれのペースで前に進んでいけます。
今を否定せず、親自身が気持ちを軽くすることは、子どもにとっても大きな安心になります。
少しずつでも大丈夫。今日よりも少し楽になれるように、自分をいたわりながら歩んでいきましょう。
最後に、Branch保護者さんのリフレッシュ方法をご紹介します。気分転換のひとつになりますよう。