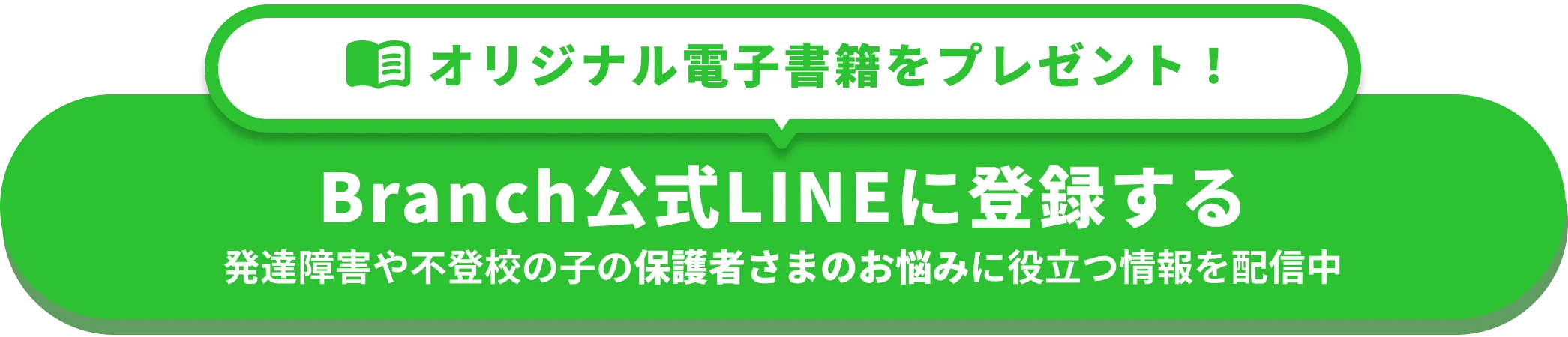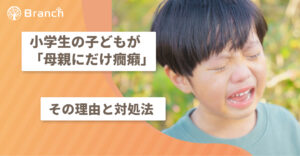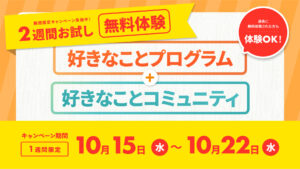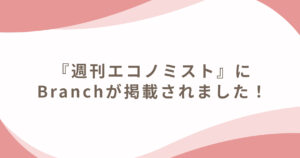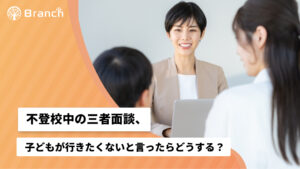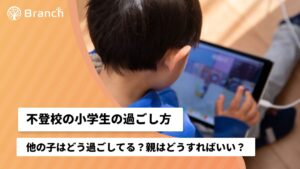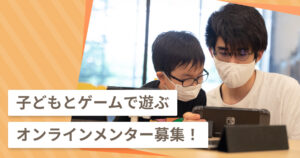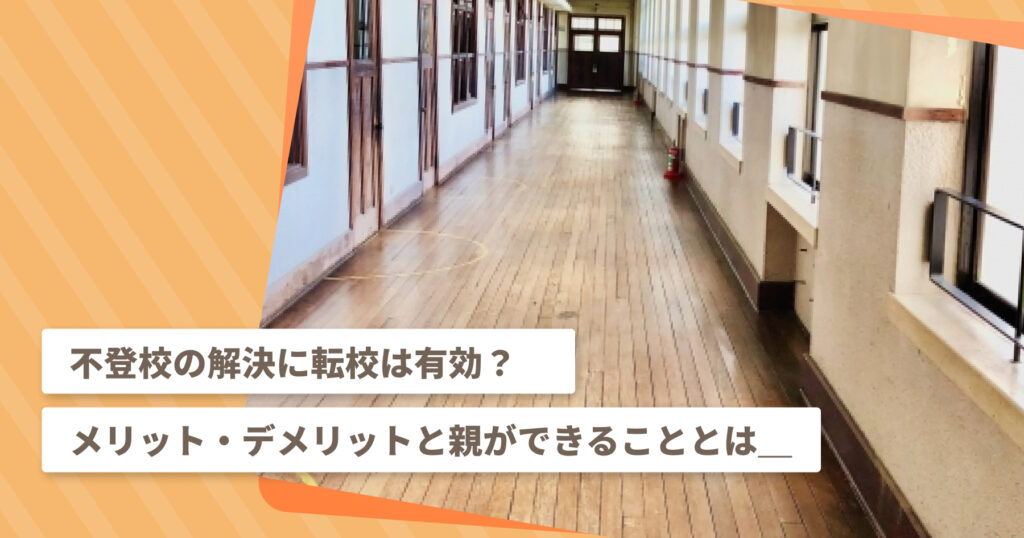
こんにちは。不登校や発達障害のお子さんと保護者さんのための居場所、Branchです。
不登校に悩む保護者の方にとって、
「このつらい状況を変えるには、環境を変えるしかないのでは」
「転校すれば、また学校に通えるようになるかもしれない」
と感じるのは、ごく自然なことです。
この記事では、転校のメリット・デメリットを整理したうえで、Branch利用者の体験談も紹介しながら、親にできることを一緒に考えていきます。
注:Branch保護者の経験談は、個人情報保護の観点から、一部、伏字にするなどしています。
転校で不登校は解決するのか?保護者が知っておきたいこと
「転校」は、不登校の根本的な解決になるのでしょうか。
その答えは、お子さん一人ひとり違います。
「不登校の解決=学校に通える」ではない
転校はゴールではなく新たなスタート地点です。「登校」を不登校のゴールにしてしまうと、どうしても「どうすれば学校に行けるか」「学校に行くためには何をすべきか」といった視点に偏りがちです。
その結果、子どもが「再び学校に行かなければ」という再登校へのプレッシャーを強く感じてしまうこともあります。
転校によって不登校がいったん解消されたようにみえても、周囲の期待に応えようと無理をしていることもあります。
何より大切なのは、お子さんが心も体も健やかに、安心して過ごせることです。
転校しても不登校が続くケースもある
「環境を変える」という選択は、前向きな一歩である反面、だれもが不安を感じるものです。 転校により生活環境が変わることが、子どもにとって新たなストレスとなり、結果的に不登校が続く場合もあります。
再登校への期待が大きいほど、「環境を変えてもダメだった」という経験が、親子にとって心の傷になってしまうこともあります。どのような経緯をたどっても、お子さんの今の状態を受け止められるといいですね。

まずは家庭を安全基地に
お子さんによっては、「今の学校」が合わないだけでなく、しばらくゆっくり休んで心と体のエネルギーを回復する時期だということもあります。
転校がお子さんにとって良いきっかけとなることもあれば、ならないこともありますが、どんなときでも、家庭をお子さんが安心できる安全基地にすることを忘れないでおきたいですね。
不登校の原因から考える転校のメリット・デメリット
転校は、お子さんが自分らしくいられる場所を見つけるための環境調整のひとつです。
転校を考えるときは、まず「なぜ不登校になったのか」を振り返ることが大切です。
背景を整理していくことで、
- 環境をどのような方向で整えていけばいいのか
- 転校が前向きな一歩につながるかどうか
が見えてきやすくなります。
なぜ不登校になった?不登校の主な原因
不登校の原因は一つとは限りません。
いくつもの要因が重なっていることもあり、丁寧に見ていくことが大切です。
特定の友だちからのいじめやいやがらせ、集団の雰囲気になじめないことなどが、学校へ行きたくない大きな要因となることがあります。
先生と相性が合わずコミュニケーションがうまくいかなかったり、声かけや指導にとまどいや不安・恐怖を感じることが、不登校のきっかけになる場合もあります。
授業のスピードが速すぎる・遅すぎる、集団学習への苦手感、厳しすぎる、あるいは自由過ぎる校風やクラスの雰囲気になじめないなど、学校システムとのミスマッチも考えられます。
朝起きられないなどの身体的な不調、家庭内の問題、感覚過敏や発達特性による困難さなど、目に見えにくい原因が隠れていることもあります。
◆参考:不登校のこどもの育ちと学びを支える当事者実態ニーズ全国調査(NPO法人 多様な学びプロジェクト)
 保護者
保護者うちは小学校〇年〜〇年の時にトラウマに悩まされましたが、2年くらいで解放されました。
原因は怒鳴る年配の先生がいたクラスにいたからでした。
小学校〇年〜〇年の支援級の先生だったのですが。あまりにクローズドの世界で環境も支援も良くないため、思い切って転校しました。
転校のメリット
転校により環境がリセットされ、お子さんにポジティブな変化がみられることがあります。
①人間関係のリセット(友だち・先生)
いじめなどのつらい出来事や人間関係から離れ、新しい場所で一から人とのつながりをつくるチャンスになります。
不登校だったことを知る人がいない環境は、気まずさや居心地の悪さをやわらげ、前向きな一歩を踏み出しやすくしてくれます。信頼できる大人や味方になってくれる友だちとの出会いは、学校生活を楽しく過ごしやすくしてくれるでしょう。



時間がたち、本人にエネルギーが溜まったということと、中学の途中で学区外に転校したことも大きかったと思います。近所で会うかもしれない中学生=他校の人、となったことで、精神的に余裕が生まれたようです。
②新しい出会いと学びの意欲の回復
転校先によっては、先生の関わり方やカリキュラムがお子さんのニーズに合い、学びへの意欲が戻ったり、新しい出会いが興味や世界を広げてくれることもあります。



学校に行けるようになったきっかけも、〇年生の転校先の先生との関係性がよく、そこから同級生の男の子たちとの関係性ができてきて、今につながりました。
③個別最適な学びの場(少人数・支援級など)
発達特性や感覚過敏がある場合、これまでの学校では難しかった環境調整や合理的配慮などのサポートを受けやすくなることがあります。
安心して過ごせる場で小さな成功体験を積み重ねることで、自信を取り戻すきっかけにもなるでしょう。
発達特性がある子どもの転校も参考になります。



小〇で不登校になり支援級のある学校に転校したのが小5。小6の担任の先生に出会えて息子は変わりました✨彼の学校生活の中で唯一のものすごく良い先生でした✨
息子はこの先生のおかげで学校に楽しく行けるようになったし、できることが増えて自信が少しつきました。また、「無理をしなくていい」「完璧じゃくてもいい」という事を教えてもらえました。たぶん家族以外に初めて信頼して接することができた人だったと思います。
今だに、小6の時が一番良かったな…と言っています。
④過ごしやすい環境
校舎やトイレなどの設備が新しくキレイになることで、学校への不安が解消されることがあります。匂いや光・音などに過敏なお子さんは、苦手なものから自分を守りやすい環境に移ることで安心感が高まります。


転校のデメリット
転校は、子どもにとって大きな環境変化です。
一時的に不安定な様子がみられたり、再び不登校になることもあるでしょう。
①環境変化そのものがもたらす負担
転校により、クラスメイト、先生、校内ルールなど取り巻く環境が全てリセットされ、慣れない場所で新たに自分のペースを見つけていくことになります。
引越しをともなう転校であれば、見知らぬ土地での生活自体が負担になることもあります。
②新しい人間関係をつくる難しさ
すでに出来あがっている友だちの輪に入るのは、大きな勇気がいることです。
新しい環境になじむまで時間がかかったり、孤立感から再び学校へ行くことをためらってしまうこともあるかもしれません。
③学習進度やレベルの違いによるプレッシャー
学校間で授業のスピードに差があったり、学習内容や授業スタイルが違うことがあります。学習の遅れを感じたり、差を埋めることに対してプレッシャーを感じてしまうことがあります。
④通学手段の変更
地元の学校から転校するケースなどでは、転校にともない通学時間が長くなったり交通手段が変わることがあります。通いやすさは子どもだけの問題でなく、送迎などが必要なケースなどでは家庭のサポートにも関わってきます。
⑤元の環境に戻ることが難しい
転校先があわなかった場合でも、元の学校に戻ることは簡単なステップではありません。転校を繰り返すことで自信をなくしてしまったり、心理的にも元の学校には戻りにくいということもあるでしょう。
■参考記事:不登校の子どもの居場所を紹介~家や学校以外の「安心できる場所」の見つけ方
転校を安心な選択にするために親ができること
子どもが安心して新しい学校生活を過ごすために、親はどんなサポートができるでしょうか。
心の回復を最優先に、親子関係の安定を
転校は、大きなエネルギーを必要とする出来事です。
不登校の子どもが新しい一歩を踏み出すとき、心と体の元気が回復していることが欠かせません。まずは、しっかりと休んでエネルギーを蓄え、家庭が安心できる場所であることを大切にしましょう。
親子の関係が落ち着いていると、子どもが新しい環境でつまずいたときにも支えになるほか、「またチャレンジしてみよう」という前向きな気持ちを育む土台にもなります。
■参考記事:親ができる不登校への対応を8つ紹介~子どもが不登校になったときに知っておきたいこと
■参考記事:不登校の子どもが寝てばかり…親ができる対応と回復へのステップ
子どもの気持ちを確認する
転校を決めるうえで、お子さん自身に「転校したい」という気持ちがあるかどうかを確かめることはとても大切です。
親の思いだけで決めてしまうと、うまくいかないこともあります。
たとえ不登校であっても、
・仲の良い友だちと離れたくない
・「また同じことが起きたらどうしよう」「友だちできるかな」と先の見えない不安がある
・「自分がうまくいかなかったせいで転校するんだ」と受け止めている
など、転校に前向きになれない理由を抱えていることもあります。
普段から子どもの話を否定せずに聴くなど、子どもが自分の気持ちを話しやすい関係になっておくことも大切です。
お子さんの不安や期待に耳を傾けながら、親子でじっくり話し合う時間を持てるといいですね。


環境変化の負担を減らす
転校のように生活が様変わりする環境の変化は、子どもにとってストレスが大きいものです。
転校前から負担を和らげる工夫ができると安心です。
転校のタイミング
年度の区切りやクラス替え・進級の時期などは、まわりの子どもたちも新しいスタートを切るタイミングです。その分、人間関係を築きやすく、環境になじみやすい場合もあります。
お子さんにとって負担の少ない時期やタイミングを意識して、転校を検討していけるといいですね。
学校見学で新しい生活をイメージ
転校前には、親子で新しい学校を訪れてみるとよいでしょう。学校の雰囲気や通学路を一緒に確認することで、これから始まる生活をイメージしやすくなります。
「〇〇なところがいいね」「〇〇な活動ができそうだね」といったように、何げない声かけで、お子さんが安心できる情報を共有するのもおすすめです。
学習の遅れをサポートする体制
学習の進み具合に不安があるときは、学校側ともよく確認しあうことが大切です。
学習につまずきがあった場合に、お子さんが気軽に相談できる先(家庭教師や学習塾など)をあらかじめ確保しておくのも一つの方法です。
親が期待しすぎない
「転校すれば学校に通うようになるかもしれない」といった親の期待がプレッシャーになることもあります。
いきなり朝から毎日登校することは考えず、少しずつ無理のないペースで慣れていけばいい、と親が気楽に構えることが焦る気持ちへのブレーキにもなります。
転校に向けて生活リズムを整えていくときも、時間をかけて取り組めるといいですね。
相談先の確保
転校後に困りごとができたときも、スクールカウンセラーや地域の相談機関など、すぐに頼れる相談先とつながっておくことは親子ともに安心材料になります。
学校以外のサードプレイスがあると心強いですね。



〇〇さんご家族も転校の可能性もあるのですね。そう考えると、例え遠方に引っ越しても変わらず所属していられるオンラインのコミュニティって貴重ですよね。つくづく、Branchに繋がれた自分を褒めなきゃ✨
発達特性がある子どもの転校
不登校になってから発達特性がわかるケースは少なくありません。
現在の学校環境が子どもの特性とミスマッチで、必要なサポートを受けられないことで失敗体験が続いたり自己肯定感が育ちにくい状況にある場合は、転校を検討してみるのも一つの手です。
本人の目線で見通しを立てる
発達特性を持つ子どもは、環境の変化に敏感でストレスを感じやすい傾向があります。
学校見学を重ねるなかで、転校先の校舎・教室の構造やレイアウト、クラスメイトや先生の雰囲気、通学ルートなどを確認できると安心です。
また、特性のあるお子さんは、思いがけないことを不安に感じている場合もあります。本人の目線で、わかりやすい見通しを立てることが大切です。
受けられるサポート・合理的配慮を確認する
お子さんに個別のサポートが必要でも、在籍校に支援級がない場合や、通級利用のために離れた学校まで通わなくてはならない場合があります。特別支援を求めて転校する際は、あらかじめ転校先の学校で受けられるサポートを確認しておくようにしましょう。
また、子どもが苦手なことや効果的だった支援方法など、学校と家庭で共通の理解を持つことは、学校生活で新たな困りごとができたときにも役に立ちます。
サポートブックなどの活用もおすすめです。
■参考記事:【実例あり】子どもが支援級を勧められたらどうすればいい?学級選びのポイントや将来の進路について
■参考記事:「発達障害や不登校の子どもが安心して学校に通えるための合理的配慮の方法」
新しい環境に慣れるときはスモールステップで
新しい環境には「短い時間から始める」「週に〇回だけ登校してみる」など無理のないスモールステップで慣れていくのがおすすめです。教室以外にも、別室や保健室などの安心できる場所があると、自分でペースを調整しながら慣れていきやすいかもしれないですね。
学校そのものが合わない場合もある
小規模校への転校や支援級のある学校への転校をきっかけに、「学校生活を楽しめるようになった」という声は、Branchコミュニティの中でも聞かれます。
一方で、特性からネガティブな記憶が残りやすく、不登校になった時点で学校そのものに苦手感ができている場合などは、転校してもうまくいかないことがあります。
学校という枠組みそのものが特性にマッチしないこともあるでしょう。フリースクールなど、学校以外の選択肢にも目を向けてみることが必要な場合もあります。


転校手続きの進め方:スムーズな移行のために
転校手続きは、どのような流れで進めていくとよいのでしょうか。
事前の相談と情報収集
まずは保護者さんが情報を集めることから始まります。
関係先にあらかじめ相談しておくことは、その後の手続きをスムーズに進めるうえで助けになるでしょう。
在籍校や教育委員会との相談・調整
転校を考えている場合は、早めに在籍校の先生やスクールカウンセラー、教育委員会の相談窓口に話をしてみましょう。
手続きやスケジュールの確認ができるだけでなく、今の状況に合ったアドバイスをもらえることもあります。
転校先の情報収集
候補となる学校の校風や、子どもたちの過ごしている様子を知るために、少しずつ情報を集めてみましょう。
自治体のホームページや学校の公式サイトを見てみるほか、実際に校舎に足を運んで雰囲気を感じたり、お子さんとの相性を確かめてみるのもよいですね。
また、在校生の保護者の話を聴くと、より具体的に学校生活がイメージできるでしょう。
現在の学校と転校先との情報共有・連携
相談の段階から、子どもの性格や得意・不得意、不登校に至った背景やこれまでの学習の様子を伝えておくと、受け入れ先の学校も対応しやすくなります。これまで通っていた学校とも連携できる体制を整えておけると安心ですね。
学校とのやりとりに負担を感じる場合は、スクールソーシャルワーカーなどの専門機関にサポートをお願いするのも一つの方法です。
■参考記事:学校で、次年度の引き継ぎはどのようにしていますか?【不登校】



半年ほど前に、教育支援センター(教育委員会内)に別件で電話をした時に、転校についてさらりと聞いてみました。
回答は、不登校の場合の越境転校は認められないことが多いということでした。そもそも、越境自体がハードルの高い自治体なのかも、です。例えば、親の就労の都合上、隣接学区にある祖父母宅から通学・帰宅することになるなどの理由だと、通りやすいということでした。
あと、不登校の場合、転校して復学できたケースが、残念ながら少ない、ということも言われました。
それで、先月にスクールカウンセラーさんとの面談において、中学進路相談からの流れで、転校の話になりました。学区内の中学校には情緒級がなく、支援級を選択する場合は隣接学区の中学校に通うことになるので、ある意味転校に近い状態になるんですね。
で、小学校のうちに転校も考えなくはないんですけどね〜、教育支援センターに聞いてみたら、不登校が理由だとハードル高いって言われちゃった、と伝えたら、「そんなことはないですよ。実際に転校している子もいるしね」って。それで、「理由はね、作るのよ」って。ちょっとニヤリとしてた感じがする笑。
本人にとって、同級生は知らない子の方がいいのか、知っている子の方がいいのか、確認していきたいね〜と。
あとは、意外に校舎や雰囲気で決まっちゃう子(ここなら行きたい)もいるから、見学は行きたいね〜という話も出ました。
確かに、校舎やトイレが新しくて綺麗ってだけで通えるようになった話も聞くので、過敏があったりすると、ハコモノとの相性もありそうだな〜と個人的には思ったりもします。
実際の事務手続きの流れ
転校に必要な手続きは、公立か私立かによって、また引越しの有無やお住まいの自治体によっても異なります。
細かな点については、直接関係先に問い合わせて、確認しながら準備を進めていけると安心です。
■一般的な転校手続き



今日、校長に相談して転校申請してきました!
(途中省略)
昨年、在籍校の校長からは
・本人の意思で転校を希望する場合
・転校で不登校の状態が改善される見込みがあること
上記の2つが揃えば、年度途中でも申請書類は書けると聞いていました。
この度、本人の意思と、通級でその学校に通えている実績も揃ったので、転校申請に踏み切りました。
今日は在籍校のSSWさんに相談するだけのつもりでしたが、校長と教頭がちょうど居たので、SSWさんに同席してもらって話を進めてきました。
SSWさんは転校先にも行っているとのことで、かなり心強い味方になってくれそうです😊
あとは教育委員会の判断になるのですが、なんとかひとつ目のハードルを超えました😂
注:SSW=スクールソーシャルワーカー
まとめ
不登校は、親子にとって先の見えない不安を感じるものです。
「転校した方がいいのでは」と悩む気持ちは、お子さんの未来をより良いものにしたいという、親の愛情や願いの表れだと思います。
転校は不登校を自動的に解決するものではありませんが、環境を大きく変えることで、子どもの可能性を広げるためのチャンスにもなります。
子どもの気持ちやタイミングを大切にしながら、お子さんにとってより良い環境を選んでいけるといいですね。
「好き」で安心とつながりを育むサードプレイス
この記事を書いているBranchは、不登校・発達障害のお子さま向けのオンラインサービス「Branch home+」を運営しており、以下の特徴があります。
- 子どもが安心できるメンターと、1対1で好きなことを好きなだけ楽しむ「好きなことプログラム」
- オンラインツールをつかった、学校外で友だちができるコミュニティサービス「好きなことコミュニティ」
- NHKや日テレなど多くのメディアにも紹介され、本田秀夫先生との対談や、厚生労働省のイベントの登壇実績もある。
Branch home+は無料体験ができるので、ご利用を迷われている方は一度お気軽にお申し込みください。
また、不登校や発達障害に関する情報を日々シェアしているLINEも運営しております。こちらも無料ですので、よろしければご登録ください。